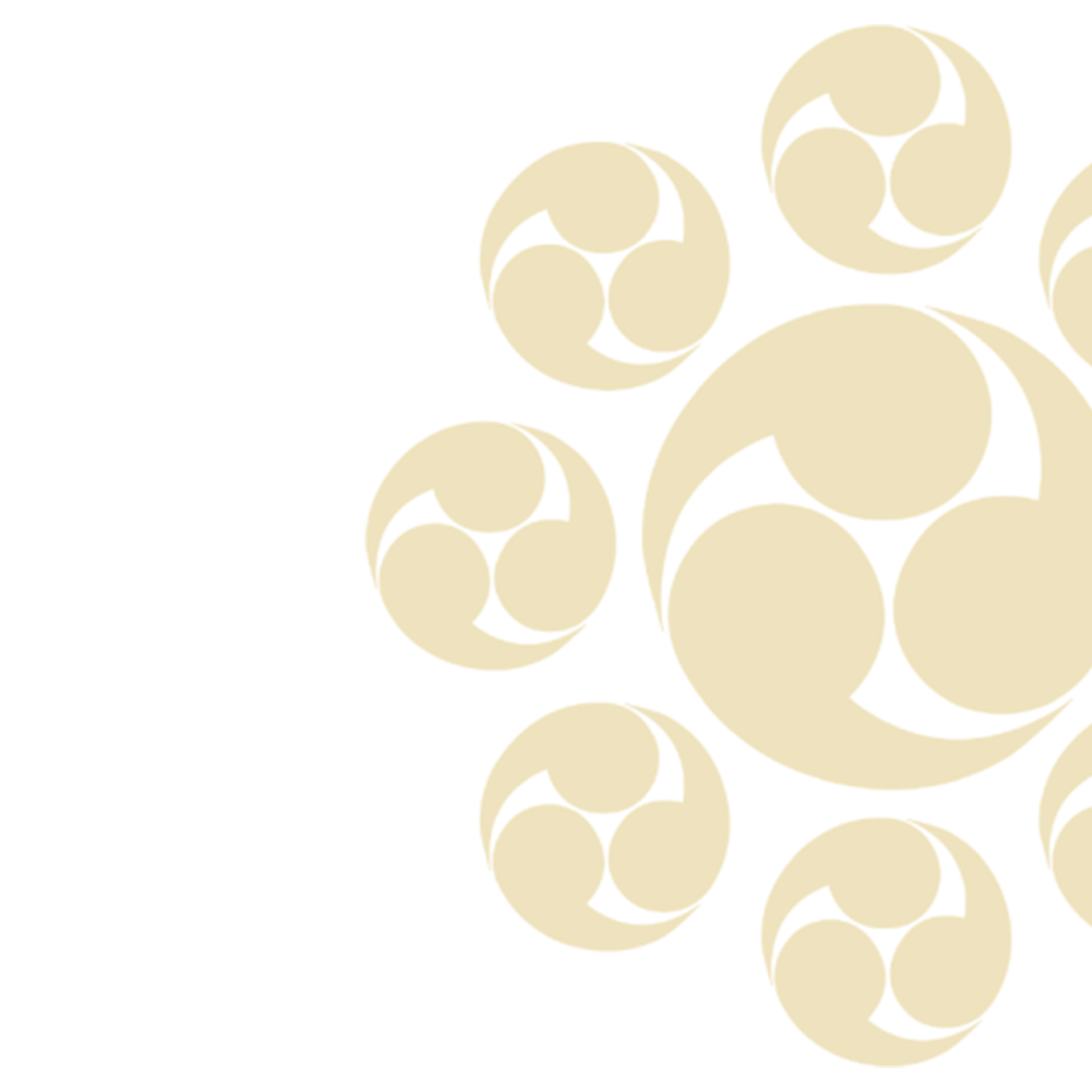2025-07-18
京都点心福の献立帖
焼売を包む手と、鳥居の継ぎ目に見る職人のこころ

🍽️【本日の献立】
主菜:昔ながらのしゅうまい(京都点心福)
副菜:とうもろこしとズッキーニの揚げびたし
汁物:賀茂なすと鱧のすまし汁
ご飯もの:鰻の炊き込みご飯
京都の町を歩いていると、ふと足を止めたくなるのが、古い鳥居の継ぎ目の美しさ。
それは、私たちが包む焼売のヒダにも似ていて、見えない部分にこそ、心を込める大切さを教えてくれるようです。
今夜は、そんな静かな想いを胸に、京都点心福の「昔ながらのしゅうまい」で、心やわらぐお献立を仕立ててみました。
---
📜 本日の献立(分量と作り方)
---
🥟 主菜:昔ながらのしゅうまい(京都点心福)
材料(2人前)
昔ながらのしゅうまい(京都点心福):6個
作り方
1. 蒸し器で7〜8分。
2. フライパンでも、水を加えて蒸し焼きにしても美味しく仕上がります。
> もっちりとした豚の旨味と、シャキッとしたクワイの歯ざわりが、ひと口に沁みます。
---
🌽 副菜:とうもろこしとズッキーニの揚げびたし
材料(2人前)
とうもろこし(実を外す):1/2本
ズッキーニ:1/2本(輪切り)
揚げ油・出汁・薄口醤油・みりん:各適量
作り方
1. 野菜を素揚げし、熱いうちに出汁で調味したつけ地に浸します。
2. 冷やしておくと、夏にぴったりの冷たい副菜になります。
---
🍲 汁物:賀茂なすと鱧のすまし汁
材料(2人前)
賀茂なす(輪切り):1/2個
鱧の落とし:4切れ
出汁:400ml
薄口醤油:小さじ1
塩:少々
作り方
1. 賀茂なすを焼いてから出汁に入れ、鱧を加えて温めます。
2. 調味して、すまし汁に仕立てます。
---
🍚 ご飯もの:鰻の炊き込みご飯
材料(2人前)
米:1合
鰻の蒲焼(市販):1/2尾
刻み生姜:小さじ1
酒・みりん・醤油:各小さじ1
出汁:180ml
作り方
1. 調味した出汁と米を合わせて炊飯します。
2. 鰻を刻んで加え、炊き上がりに軽く混ぜます。
---
🔑 本日のキーワード
京都 お取り寄せ
京都点心福
昔ながらのしゅうまい
シュウマイ レシピ
---
✍️ 本文
🏯 鳥居の「継ぎ目」や「切れ目」にまつわる秘密
木材の収縮と反りを防ぐための構造
一本木をそのまま使うと、気温や湿度の変化で反ったり割れたりしやすいため、複数の部材を継いで組み合わせている。
部材の交換を前提とした設計
腐食や風雨による劣化に備え、傷んだ部分のみを交換できるように、分割して作ることが多い。
「込栓(こみせん)」という技術で接合
柱や貫(ぬき)を木製のダボや楔でしっかりと固定する、伝統建築の技法が用いられる。
「包板(つつみいた)」で見た目を整えることも
継ぎ目が目立たぬよう、薄い木板で覆うこともあるが、あえて見せることで構造美を強調することもある。
鳥居の種類によって構造が異なる
神明鳥居(直線的)や明神鳥居(反りがある)など、形式により接合部の見せ方も異なる。
切れ目は「傷」ではなく「意図的な継手」
よく見ると直線的なラインであり、木工職人が意図して仕込んだ“技術”の証でもある。
地震対策としての“遊び”のある構造
柔軟性を持たせることで、地震の揺れにも耐える構造にしている例もある。
古来より「継ぐ」ことは縁起が良いとされる
継ぎ木や継手には「つながり」や「再生」の意味も込められ、神事にふさわしい意味合いを持つ。
主菜:昔ながらのしゅうまい(京都点心福)
副菜:とうもろこしとズッキーニの揚げびたし
汁物:賀茂なすと鱧のすまし汁
ご飯もの:鰻の炊き込みご飯
京都の町を歩いていると、ふと足を止めたくなるのが、古い鳥居の継ぎ目の美しさ。
それは、私たちが包む焼売のヒダにも似ていて、見えない部分にこそ、心を込める大切さを教えてくれるようです。
今夜は、そんな静かな想いを胸に、京都点心福の「昔ながらのしゅうまい」で、心やわらぐお献立を仕立ててみました。
---
📜 本日の献立(分量と作り方)
---
🥟 主菜:昔ながらのしゅうまい(京都点心福)
材料(2人前)
昔ながらのしゅうまい(京都点心福):6個
作り方
1. 蒸し器で7〜8分。
2. フライパンでも、水を加えて蒸し焼きにしても美味しく仕上がります。
> もっちりとした豚の旨味と、シャキッとしたクワイの歯ざわりが、ひと口に沁みます。
---
🌽 副菜:とうもろこしとズッキーニの揚げびたし
材料(2人前)
とうもろこし(実を外す):1/2本
ズッキーニ:1/2本(輪切り)
揚げ油・出汁・薄口醤油・みりん:各適量
作り方
1. 野菜を素揚げし、熱いうちに出汁で調味したつけ地に浸します。
2. 冷やしておくと、夏にぴったりの冷たい副菜になります。
---
🍲 汁物:賀茂なすと鱧のすまし汁
材料(2人前)
賀茂なす(輪切り):1/2個
鱧の落とし:4切れ
出汁:400ml
薄口醤油:小さじ1
塩:少々
作り方
1. 賀茂なすを焼いてから出汁に入れ、鱧を加えて温めます。
2. 調味して、すまし汁に仕立てます。
---
🍚 ご飯もの:鰻の炊き込みご飯
材料(2人前)
米:1合
鰻の蒲焼(市販):1/2尾
刻み生姜:小さじ1
酒・みりん・醤油:各小さじ1
出汁:180ml
作り方
1. 調味した出汁と米を合わせて炊飯します。
2. 鰻を刻んで加え、炊き上がりに軽く混ぜます。
---
🔑 本日のキーワード
京都 お取り寄せ
京都点心福
昔ながらのしゅうまい
シュウマイ レシピ
---
✍️ 本文
🏯 鳥居の「継ぎ目」や「切れ目」にまつわる秘密
木材の収縮と反りを防ぐための構造
一本木をそのまま使うと、気温や湿度の変化で反ったり割れたりしやすいため、複数の部材を継いで組み合わせている。
部材の交換を前提とした設計
腐食や風雨による劣化に備え、傷んだ部分のみを交換できるように、分割して作ることが多い。
「込栓(こみせん)」という技術で接合
柱や貫(ぬき)を木製のダボや楔でしっかりと固定する、伝統建築の技法が用いられる。
「包板(つつみいた)」で見た目を整えることも
継ぎ目が目立たぬよう、薄い木板で覆うこともあるが、あえて見せることで構造美を強調することもある。
鳥居の種類によって構造が異なる
神明鳥居(直線的)や明神鳥居(反りがある)など、形式により接合部の見せ方も異なる。
切れ目は「傷」ではなく「意図的な継手」
よく見ると直線的なラインであり、木工職人が意図して仕込んだ“技術”の証でもある。
地震対策としての“遊び”のある構造
柔軟性を持たせることで、地震の揺れにも耐える構造にしている例もある。
古来より「継ぐ」ことは縁起が良いとされる
継ぎ木や継手には「つながり」や「再生」の意味も込められ、神事にふさわしい意味合いを持つ。
PDFを開く
一覧へ戻る